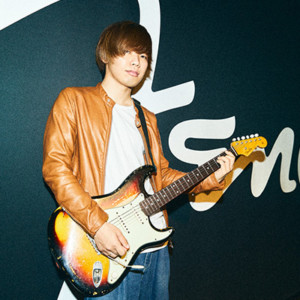Signature Model Interview | J(LUNA SEA) -前編-
自分の音楽人生の中でも大きな意味を持つこの色を、フェンダーのベースに託したかった
“炎”を宿す赤が、再びJのベースに宿る──。フェンダーとの共同制作によって誕生したシグネイチャーモデル第3弾、Limited Edition Masterbuilt J PRECISION BASS® King’s Red SparkleとLimited Edition Masterbuilt J PRECISION BASS® PJ, King’s Red Sparkle。J自身が“象徴的な色”と語る赤をまとったこのモデルには、彼の美学とプレイヤーとしての哲学が詰まっている。その開発背景から、細部にまでこだわり抜かれた仕様を本人が解説する。
フェンダーが築いてきた“王者にしか歩めない重み”。そうした存在に自分自身の敬意を込めた
──まずは今回のシグネイチャーモデルのカラーをKing’s Red Sparkleにした理由から聞かせてください。
J 僕がバンドを始めた当初から、“赤いベースを持っている”というイメージを持ってくれている人は多いと思います。実際、自分でも燃えるようなそのイメージは大切にしている部分で、ソロアルバムのタイトルにも炎をモチーフにした『PYROMANIA』を冠しました。そういった意味で赤という色は、自分にとって特別で、象徴的なもの。今回のKing’s Red Sparkleは、そんな赤という色をあらためて全面に打ち出したくて、マスタービルダーのグレッグ・フェスラーにオーダーして作ってもらいました。
フェンダーのベースを使わせてもらうようになってからは、その伝統や歴史、変わらない情熱や信念に、どう自分らしく向き合っていくかを常に考えてきました。Black Gold、Champagne Goldとモデルを重ねる中で、それぞれの個性を自分のサウンドとして体得してきたという実感があります。だからこそ、今回は満を持して赤に挑みました。自分の音楽人生の中でも大きな意味を持つこの色を、フェンダーのベースに託したかったんです。
──赤にもさまざまなトーンがありますが、今回のKing’s Red Sparkleにはどんな思いを込めたのでしょうか?
J たとえばKing’s と名付けたのは、つまり王者が纏うもの。王冠やマントなどに使われる“王者の名を冠したもの”が持つ、気品や威厳といったロイヤル感を重ねています。赤という色に対する自分のこだわりと、フェンダーが歩んできた王道の精神が、自分の中で自然と重なった感覚がありました。“王道”という言葉は簡単に口にできますが、本当の意味での王道には、誰にも真似できない強さや覚悟が必要です。周囲に左右されず、我が道を突き進む姿勢こそがそれを支えている。フェンダーが築いてきた歴史には、まさに“王者にしか歩めない重み”があります。そうした存在に自分自身の敬意を込めたつもりです。王冠の赤、マントの赤、そして情熱の赤。そうした“ロイヤルな赤”のイメージを、このスパークル仕上げの中に閉じ込めたいと。
──どのカラーにも、Jさんの一貫した美学と哲学がありますね。
J ありがとうございます。自分の中ではスパークルのフィニッシュが昔から本当に好きで、マニアみたいにそういうものばかり集めていた時期もありました(笑)。家具もそうだし、例えば事務所に置いていたソファもスパークル仕様。70年代っぽいテイストにも通じる、あのキラキラ感に、なぜか昔から惹かれてしまうんですよね。ある意味スパークル“フェチ”なんです(笑)。
──そのきらびやかさとは対照的な、ヘヴィレリック仕様との組み合わせも印象的です。
J 今回も色のイメージをグレッグに伝えたところ、仕上がってきた実物を見て本当に驚きました。サウンドだけでなく、楽器としての佇まいにまで強いこだわりが感じられて、あらためてグレッグはフィニッシュにも魂を込める本当に芸術的なビルダーなのだなと実感しましたね。今回の塗装は、マットな質感に仕上げています。艶(ツヤ)を抑えた中に、ほんのりとスパークルが浮かび上がる。最初は“ファイヤーレッド”と呼んでいたのですが、本当に“炎の中をくぐり抜けた”ような、焼け焦げたようなニュアンスのある仕上がりなんです。
──確かにそうですね。
J そもそも、スパークル仕上げでヘヴィレリック仕様という組み合わせは、ほとんど市場に存在しないと思うんですよね。製作自体もかなり大変だったはずですし、下手をすると取って付けたような仕上げに見えてしまいがちなんですが、今回も全くそうならなかった。例えば、ピックガードに使っているパール素材にもしっかりとエイジング加工がされていて、ほんのり茶色がかっていて、長い月日を経た日焼けのような自然な風合いが出ている。もう、眺めているだけで2〜3日過ごせるくらい、見飽きないんです(笑)。
──ネックの形状も、一般的なプレベとは少し違いますよね。
J いわゆる普通のPrecision Bassと比べると、ネックの太さはプレベとジャズベのちょうど中間くらい。両方の良さをバランスよく取り入れたような設計になっていて、自分としてはとても扱いやすいですね。プレベよりもシャープで、Jazz Bassよりも太く響く、その絶妙なバランスが気に入っています。動きの多いプレイスタイルにもフィットするし、女性ベーシストにも扱いやすいサイズ感だとよく言われます。最近は女性プレイヤーも本当に増えてきたので、ぜひそういう方たちにも試してみてほしいですね。
──ネックのピッチやフレットとのバランスも絶妙です。
J フレットの太さとネックのバランスが本当にすごく良くて、いつも手にした瞬間から違和感なく馴染むんです。例えばヴィンテージのベースだと、ネックが太すぎたり細すぎたりして、弾きづらさを感じることもある。でもこのモデルは、ヴィンテージライクな雰囲気を保ちながら、扱いやすさにしっかり配慮されているんです。しかも、“芯が出る”というか、しっかり鳴ってくれる頼もしさがある。とても洗練されたネックだと思いますね。

音、質感、感触──すべてが絶妙なバランスで共存している
──楽器としてのサウンド面はどうでしたか?
J これまでのモデルと比べて、King’s Red Sparkleはまたまったく違った響きでした。まるで“フェンダーからの新たな回答”が届いたような感覚です。弾き始めてすぐに感じたのは、手元のニュアンスがそのまま音になるということ。フレットや指板にわずかに触れた時のテンションから、ナチュラルなドライブ感や歪みが生まれ、それが非常に繊細に音に反映されるんです。それも出力で無理に押すようなものではなく、楽器自体の“鳴り”の中から自然に立ち上がってくるドライブ感なんですよね。
ベースって、一般的には“力を入れないと鳴らない”というイメージがありますよね。4弦の太さゆえに、しっかり弾き込まないと音にならない。でもこのKing’s Red Sparkleは全然違うんですよ。軽いタッチでも反応してくれるし、表情をつける余白がしっかりある。こういう楽器って、ほんとになかなか出会えないです。しかも、手巻きのピックアップがその繊細なニュアンスをしっかり受け止めてくれる。音、質感、感触──すべてが絶妙なバランスで共存していて、本当に完成された一本だと思います。
──今回、新たにPJ(プレシジョンベース×ジャズベース)という構成でのモデルも制作されましたが、その意図や狙いについて教えてください。
J プレベを長く使ってきた中で、“もう少し芯を出したい”と思う場面が時々あったんです。それまでは、指のタッチやアタックで芯を作ってきましたが、そこにJazz Bassのピックアップを加えたら、どんな変化が起きるんだろうと。いわゆるPJ仕様によって、より自然に芯が前に出るようなサウンドが作れるんじゃないか。そう考えて、グレッグにオーダーしたのが始まりです。
──特にこだわった部分は?
J まず、自分にとって指板での音の跳ね返りはすごく重要なポイントで、それを生み出すメイプルネックは外せませんでした。そこは自分のサウンドの個性にも直結する部分なので、迷いなく採用しています。あとはボディ材ですね。手元にあるPベースはアッシュ材なのですが、アッシュはどちらかというと腰高な響きになる印象があります。あえてその傾向を利用して自分のサウンドにしているのですが。ただ、そこにジャズべのピックアップを載せると、自分が求める芯の位置が少し上ずってしまうように感じたんです。
──その結果、PJモデルではアルダー材に変更したと。
J はい。今回はボディをアルダー材でオーダーしました(※注:P Bassはアッシュ材)。その判断が大正解で、レンジが少し下に落ち着いたぶん、低域にまとわりつくような“重さ”が加わって、その上でしっかりと埋もれない芯のある理想的なサウンドになりました。自分にとって非常に意味のあるバランスで、グレッグのクラフトマンシップと僕の好みがまた一段と噛み合った、理想的な一本になったと思っています。

Limited Edition Masterbuilt J PRECISION BASS, King’s Red Sparkle | Limited Edition Masterbuilt J PRECISION BASS PJ, King’s Red Sparkle
>> 後編に続く(近日公開)
J
小野瀬 潤 1992年にLUNA SEAのベーシストとしてメジャーデビュー。「ROSIER」「TRUE BLUE」「STORM」などの原作者として数々のヒットを生み出し、ベーシストとしても孤高の存在感を放ち、自身のモデルベースは世界のアーティストモデルの中でも1位の売り上げを誇る。1997年にはLUNA SEAの一時活動休止を機にソロ名義での活動をスタートし、1st アルバム『PYROMANIA』を発表。2000年のLUNA SEA終幕を経て2001年にソロ活動を再開すると、海外から多数のアーティストを招き開催したライヴ・イベント“FIRE WIRE”、アリーナをオールスタンディングにして開催した史上初の日本武道館公演など、他に類のない独自のスタイルでライヴ活動を展開。2019年5月にはLUNA SEA結成30周年を迎えた節目に、世界的楽器メーカーであるフェンダーとのワールドワイドなエンドースメント契約を発表。2025年1月発行のベースマガジンで企画された「プロ・ベーシストが選んだ偉大なるベーシスト100人」では、世界中の錚々たるベーシストが名を連ねる中、第10位を獲得。また、一般アンケート投票(#最も偉大なベーシスト2025)においては、堂々の1位に輝いている。2025年はLUNA SEA結成35周年ツアーのグランドファイナルとして、東京ドーム公演を開催。LUNA SEAとしても確固たるその存在を世に示した。現在も、日本のロック・ベーシストとして唯一無二のスタイルを提示し続け、LUNA SEA、ソロの両方で活躍中。
http://www.j-wumf.com